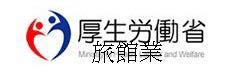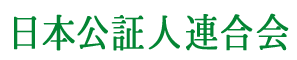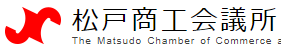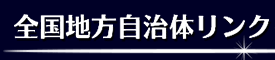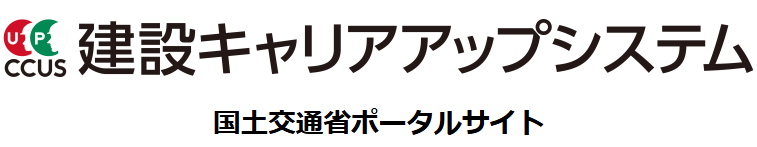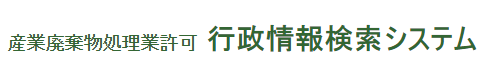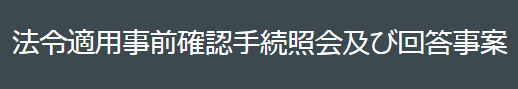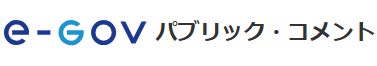千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
営業時間 | 10:00~21:00 日曜・祝日を除く |
|---|
アクセス | 京成松戸線 みのり台駅から徒歩5分 駐車場1台あり |
|---|
建設業許可

建設業許可がなくても請け負うことができる工事
建設業とは元請・下請を問わず、また法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法第2条第2項)
そして、建設業を営む者でも軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業許可は不要とされています。軽微な建設工事とは、以下の工事をいいます。
| 建築一式工事 以外 | 1件の請負代金が税込・材料費込500万円未満の工事 |
| 建築一式工事 (例:住宅の新築工事) 元請として請け負った工事 のみ該当 | ※いずれかに該当する工事 ①1件の請負代金が税込・材料費込1,500万円未満の工事 または ②請負代金額にかかわらず延べ面積150 ㎡未満の木造住宅工事(主要構造部分が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること) |
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業を営む者は建設業の許可を受けなければなりません。実際の工事は下請けに出す場合であっても許可は必要です。
(そもそも建設業法では一括下請負・工事の丸投げは禁止です(建設業法第22条))
なお「軽微な建設工事」の請負代金の額は、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格及び運送賃を、当該請負契約の請負代金の額に加えた額を指します。(施行令1条の2第3項)
ただし、税込500万円未満の軽微な工事であっても、電気工事、浄化槽工事、解体工事を行うには各法律(電気工事業法、浄化槽法、建設リサイクル法)で建設業許可とは別に登録・届出制度が定められていて手続きが必要です。
電気でいうと、電気工事の建設業許可をもっていても電気工事業の登録は必要です。建設業許可しかない場合、電気工事を元請として請ける(営業する)ことはできますが、自社で電気工事を施工することはできず、登録電気工事業者に下請けに出さなくてはなりません。
逆に電気工事業の登録のみの場合、税込500万円以上の電気工事を請け負うことはできません。
また電気工事及び消防施設工事は、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。
電気工事については、さらに電気工事業登録等も必要です。
電気工事士法及び消防法の規定により、無資格者による電気工事又は消防施設工事の実務経験は認められません。
建設業の種類
一口に建設業と言っても、とび・土工、大工、塗装、電気工事、解体など様々な業種があります。
建設業の許可は全29業種に分かれていて、業種ごとに許可を受けることが必要です。いくら土木工事業、建築工事業といった一式工事の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、税込500 万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。
<建設業の全29業種>
- 1土木工事業
- 2建築工事業
- 3大工工事業
- 4左官工事業
- 5とび・土工工事業
- 6石工事業
- 7屋根工事業
- 8電気工事業
- 9管工事業
- 10タイル・れんが・ブロック工事業
- 11鋼構造物工事業
- 12鉄筋工事業
- 13舗装工事業
- 14しゅんせつ工事業
- 15板金工事業
- 16ガラス工事業
- 17塗装工事業
- 18防水工事業
- 19内装仕上工事業
- 20機械器具設置工事業
- 21熱絶縁工事業
- 22電気通信工事業
- 23造園工事業
- 24さく井工事業
- 25建具工事業
- 26水道施設工事業
- 27消防施設工事業
- 28清掃施設工事業
- 29解体工事業
建設業許可の区分(特定建設業と一般建設業)
また業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
自社が下請の場合、また元請でも下請に出す金額が税込5,000万円未満(建築一式工事では8,000万円未満)の場合は、一般建設業に該当します。
同じ建設業者が複数の業種の許可を持っていて、舗装工事業では一般建設業、土木工事業では特定建設業ということもありますが、令和6年3月末時点で約48万近くある建設業許可業者のうち、特定建設業許可を取得しているのは49,029業者と1割弱です。
| 特定建設業 令和7年2月1日改正 | 元請として発注者(施主)から直接請け負う1件の工事につき、下請に出す金額が税込5,000万円以上(建築一式工事は税込8,000万円以上)(材料費は含めない)となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合、特定建設業に区分され、特定建設業の許可が必要となります。 |
| 一般建設業 | 上記の金額制限に該当しない元請業者や下請け業者は、一般建設業の許可となります。 ①税込5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満) ②工事のすべてを自社で施工 |
| 従前 | 令和5年1月1日改正 | 令和7年2月1日改正 | |
|---|---|---|---|
| 特定建設業許可の下請代金額の下限 ( )は建築一式工事の下限額 | 税込4,000万円 (税込6,000万円) | 税込4,500万円 (税込7,000万円) | 税込5,000万円 (税込8,000万円) |
知事許可と大臣許可
建設業の許可には知事許可と国土交通大臣許可があります。
知事許可になるか、大臣許可になるかは、建設業を営む営業所の場所が基準となります。
営業所が1つのみ、または複数あっても同じ都道府県内にだけある場合は、県知事許可。
東京都内と千葉県内に2つ営業所がある場合など、2以上の都道府県にまたがって営業所を設け建設業を営む場合は、大臣許可が必要になります。
| 知事許可 | 1つの都道府県内のみ営業所を設けて建設業を営む場合 |
| 大臣許可 | 2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営む場合 |
申請してから許可が下りるまでの期間
千葉県では申請してから約45日(土・日・祝日含む)かかります。(東京都・埼玉県では約30日)
申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のこと(申請してから許可がおりるまでの期間)を標準処理期間といいますが、千葉県では特に補正等がなければ、土日、祝日を含み総日数45日間としています。ただし、審査の中で申請書類の補正や技術者の在籍状況確認等により45 日以上の期間がかかることもあります。
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き建設業の許可を望む場合は、遅くとも期間が満了する日の30日前までに、許可の更新手続をしなければなりません。
この期限30日前を1日でも過ぎると、千葉県では始末書が必要となります。
(千葉県では、有効期間が満了する90日前から更新手続の申請が可能です。東京都と埼玉県では、更新の申請は満了日の2か月前から30日前までとされています。)
手続を忘れると期間満了とともに許可の効力を失い、引き続き営業することができなくなります。
有効期間が1 日でも過ぎてしまった場合は、更新の許可申請をすることはもうできません。あらためて新規で許可を申請することになります。新たに許可を取りなおすことになるため、許可番号も変わり、行政への申請手数料も5万円から9万円に増額します。(行政書士にかかる依頼費用も、更新許可と新規許可では増額します。)くれぐれも更新期限にはご注意ください!
次のページでは、全29種の建設業・建設工事の詳細について説明していきます。
建設業許可申請手続きの料金表(税込)
| 千葉県・新規許可申請(知事許可) | 報酬165,000円+申請手数料90,000円 |
|---|
| 東京埼玉・新規許可申請(知事許可) | 報酬198,000円+申請手数料90,000円 |
|---|
| 大臣・新規許可申請 ※2つ以上の都道府県に営業所がある場合 | 報酬220,000円+申請手数料150,000円 |
|---|
| 更新許可申請(知事許可)5年ごと | 報酬88,000円+申請手数料50,000円 |
|---|---|
| 更新許可申請(大臣許可)5年ごと | 報酬110,000円+申請手数料50,000円 |
| 事業年度終了届(決算変更届)毎年 | 報酬55,000円 |
|---|
| 業種追加申請(知事許可) 実務経験の場合+33,000円 | 報酬88,000円+申請手数料 50,000円 |
|---|---|
| 業種追加申請(大臣許可) | 報酬110,000円+申請手数料 50,000円 |
| 般・特新規許可申請 (一般建設業→特定建設業) (特定建設業→一般建設業) | 報酬121,000円+申請手数料 90,000円 |
| 許可換え新規(知事許可→大臣許可)/(A県知事→B県知事) 許可換え新規(大臣→知事) | 報酬220,000円+申請手数料150,000円 報酬165,000円+申請手数料 90,000円 |
| 各種変更届 (常勤役員・営業所技術者の変更、営業所の移転等) | 報酬33,000円 |
<行政が許可を受け付ける期間>
【随時受付】
新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、般・特新規+業種追加
【有効期間が満了する90日前から30日前まで】
更新
【有効期間が満了する60日前まで】
般・特新規+更新、業種追加+更新、般・特新規+業種追加+更新
※ここまでお読みくださり、ありがとうございました。
何かご不明な点、ご相談したいことがございましましたら、お気軽にお問合せください。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お問い合わせ・ご相談は、お電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。まずはお気軽にご連絡ください。
| 営業時間 | 10:00~21:00 |
|---|
| 定休日 | 日曜・祝日 |
|---|