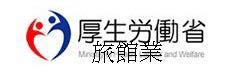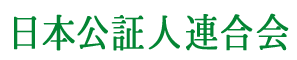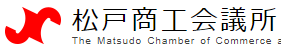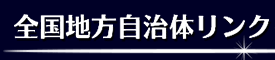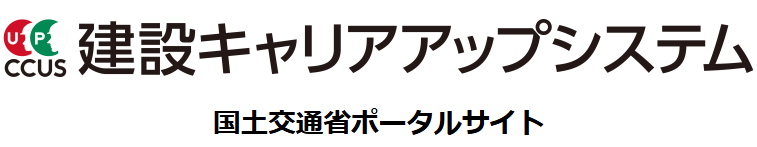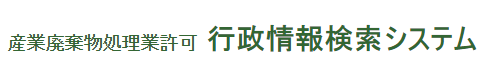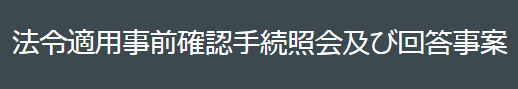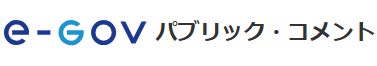千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
営業時間 | 10:00~21:00 日曜・祝日を除く |
|---|
アクセス | 京成松戸線 みのり台駅から徒歩5分 駐車場1台あり |
|---|
建設業許可のよくあるご質問
よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
工事請負契約書や注文請書を分けて作成すれば、建設業許可がない業者でも税込500万円以上の工事を請け負ってもいいですか?
認められていません。
いくら契約書を分けたとしても実態として1つの工事である場合は、一体の工事としてみなします。
また元請から資材が提供された場合、資材費と資材を運ぶ運搬費も契約代金に含めることになります。
(含めた上で税込500万円未満の工事でないと請け負ってはいけません)
例外としては新築工事があります。通常、新築工事は住宅本体の建築工事が終わると別契約で外構契約をします。住宅本体と外構は別工事で一体となっていないため、分ける契約・実態となっているのであれば可能です。
元請である自社は建設業許可を持っていませんが、実際の工事は許可のある下請業者に出すので、税込500万円(建築一式工事の場合、税込1,500万円)以上の工事でも受注して大丈夫ですよね?
貴社が元請けとして工事の契約を交わす以上、工事をしなくても税込500万円以上の工事には建設業許可が必要です。
そもそも建設業法では、一括下請負・工事の丸投げは禁止されています(建設業法第22条)
許可を取った県以外で仕事をするためには、大臣許可が必要ですか?
営業所が1つのみ、または複数営業所があっても同じ都道府県のみに点在する場合には、知事許可で大丈夫です。(大臣許可は不要です)
知事許可と大臣許可は、建設業を営む営業所の所在地が県内のみか、県外にも置くかによる区分です。したがって、営業所が1つのみ、または複数の営業所あっても同じ都道府県内のみであれば知事許可、2以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となります。
施工する工事現場の場所は関係ありませんので、知事許可の事業者でも技術者を配置して県外の現場において施工することができます。
一式工事業の許可を取得すれば、どんな工事も請け負えますか?
できません。
土木一式工事・建築一式工事の許可のみを有する建設業者が税込500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。個別の専門工事の許可が必要です。
「建築一式工事」とは、建築確認を必要とする新築及び増改築工事を元請で請負うことを指します。
例えば建築一式工事の許可のみ持っている建設業者は、税込500万円未満の軽微な工事を除いて、大工工事や内装仕上工事、屋根工事などの専門工事を請け負うことはできません。同様に、土木系も土木一式工事の許可だけ持っている建設業者は、軽微な工事を除いて、とび・土工工事や舗装工事などの専門工事を請け負うことはできませんのでご注意ください。
どんな工事をしていれば建築一式工事に該当しますか?
複数の専門工事を組み合わせて建築物を作る(解体する)工事で、工事の規模・複雑さ等によって専門工事では施工できないような工事が該当します。
建築一式工事の内容として、元請業者の立場で総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事であって、複数の下請業者によって施工される大規模・複雑な工事とされています。
一例としては①建築確認を必要とする新築工事や②建築確認を必要とする増改築工事③ビルやショッピングモールの解体工事(千葉県)など。
土木工事業・建築工事業の許可は実務経験では取れませんか?
土木工事業・建築工事業といった、いわゆる一式工事の許可でも要件を満たし、必要とされる書類を揃えられるのであれば実務経験での証明も可能です。
建築一式工事で、許可の不要な「軽微な建設工事」とされる
①1件の請負代金が税込・材料費込1,500万円未満の工事 または ②請負代金額にかかわらず延べ面積150 ㎡未満の木造住宅工事
(主要構造部分が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること)
※いずれかに該当する工事
ですが、②の「請負代金額にかかわらず」とあるので、税込1,500万円超えていても良いという意味でしょうか?
(主要構造部分が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること)
※いずれかに該当する工事
ですが、②の「請負代金額にかかわらず」とあるので、税込1,500万円超えていても良いという意味でしょうか?
はい、そうです。
一般建設業の許可で1億円の工事受注しても大丈夫ですか?
内容によります。
特定建設業許可が必要な要件は2つです。
①発注者(施主)から直接受ける場合で、かつ
②外注に出す総額が税込5,000万円以上の場合(建築一式の場合は税込8,000万円以上の場合)。
近年の工事費の高騰などにより令和7年2月1日より金額が改定しました。
詳細はこちらをご覧ください。
この2つの要件を満たす場合は特定建設業の許可が必要となり、一般建設業では受注できません。
よって、今回の例では1億円の工事でも発注者(施主)から直接受ける工事ではなく、元請がいる(自社は下請の)場合であれば受注可能です。また、発注者(施主)から直接受ける工事であっても外注に出す金額が税込5,000万円(建築一式の場合は税込8,000万円)未満であれば受注可能です。
自宅兼事務所でやっていますが、独立した営業所としてみなされますか?
居住部分とは明確に区分されているかが重要。
電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている必要があります。また、玄関等には商号を表示してください。
レンタルオフィスを建設業の営業所にできますか?
不可能ではありませんが注意が必要です!(千葉県)
①営業所としての独立性がある*(=扉を開けたらそこは建設業の書面を取り交わせる自分のみの営業所になっている)
*申請場所を行政側で確認されるケースもあり、確認の際に独立性の確保が難しいと判断されると✕
✕の例(独立性がないと判断されるケース)として
・鍵がかからない
・壁が天井まで仕切られてなく個人情報が筒抜けになるブース
②連絡が取れるところ(電話が繋がること(ケータイ電話も可)、郵便物が部屋に届くこと)
③会社名で賃貸借契約を結んでいること(部屋番号まで記載されているのが望ましい)
以上3つの条件が備わっていて、その場所で継続的に仕事をする環境が整っていると行政側が総合的に判断できれば可能とのこと。
書類を出してから許可が下りるまでにどれくらいかかりますか?
千葉県では申請してから約45日(土・日・祝日含む)かかります。
申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のこと(申請してから許可がおりるまでの期間)を標準処理期間といいますが、千葉県では特に補正等がなければ、土日、祝日を含み総日数45日間としています。千葉県では申請先が土木事務所となります。その後、県庁へ書類が送られます。内訳としては、経由機関(土木事務所)の処理10日間、処理機関(県庁)の処理35日間です。
ただし、審査の中で申請書類の補正や技術者の在籍状況確認等により45 日以上の期間がかかることがあります。(なお、更新申請についても上記によりますので、更新前の許可の満了日前に審査が終わるとは限りませんが、審査中の場合は、法律上、従前の許可(更新前の許可)が引き続き有効となる取扱です。)
ちなみに東京都では、おおむね 25 開庁日程度(土日祝日等の閉庁日を除く)、茨城県では、おおむね30日程度(土日祝日含まず)となっています。
営業所技術者等(従来の専任技術者)の実務経験証明書に記載する実務経験は、10 年間連続した経験が必要なのでしょうか?
間が空いていても、合計10 年以上の実務経験があれば大丈夫です。
連続した10 年以上の経験ではなく、実務経験の期間が不連続であっても、合計10 年以上あれば要件を満たしたものとみなされます。(なお、特定建設業許可で指導監督的実務経験が必要な場合は、契約書等に記載された工期の期間しか認められません。)
営業所技術者等(従来の専任技術者)の実務経験の証明で、指定された学科を卒業している場合に証明する実務経験期間を短縮できるとのことですが、2業種を取得したい場合も利用可能なのでしょうか?
業種ごとに指定されている学科(建築学、土木工学、電気工学、機械工学など)が異なりますが、指定学科がうまく重なるのであれば可能です。
以前に勤務していた会社と疎遠になり、代表者から証明書の押印をもらうことができない場合、申請できないのでしょうか?
在籍していた事が確認できる資料(当時の年金加入記録等)を提出して申請は可能です。
押印を求める手続の見直し等のための国土交通省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)により、建設業法施行規則の一部が改正され、提出様式への押印の廃止の動きがありました。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経験や営業所技術者等(専任技術者)の実務経験の確認資料について他社での経験を証明する場合、登記事項証明書や年金加入記録等、証明する期間中に在籍していた事が確認できる書類を提出することとなりましたので、勤務していた代表者からの押印は不要です。
ただし、従来通り、常勤役員等証明書や実務経験証明書等に以前勤めていた会社代表者の押印がある場合は、これまでと同様、実務経験期間中の常勤に疑いのある場合を除き、年金加入記録等は不要です。
実務経験証明書類として請求書と通帳の写しを提出しようと思っていますが、元請から複数の工事代金が一括して入金があり、請求書と通帳の入金額が合いません。どうしたらいいでしょうか?
一括で入金された場合、通帳に入金された他の工事の請求書も提出する必要があります。
第2種電気工事士の資格を持っているので、この資格を使って電気工事業の建設業許可を取得したいです。
注意が必要です!
まず前提として、建設業許可の29業種のうち電気工事業(消防施設工事業も同様)の場合、10年の実務経験があっても、無資格者の場合は建設業許可の営業所技術者にはなれません。これは、電気工事士法で「電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、電気工事の作業に従事してはならない」と定められているためです。実質、資格が必要な業種となるため、資格を持っていない無資格者による電気工事、消防施設工事は、10年働こうが20年働こうが営業所技術者の実務経験を積んだと認められません(そもそも電気工事法による軽微な工事を除き違法です)ので、ご注意ください。
次に、電気工事業を営む場合は、税込500万円未満の軽微な工事(建設業許可が不要な工事)であっても「電気工事業の登録」をしている必要があります。行政によっては「電気工事業の登録」以降でないと経営業務の管理責任者としての「経営経験期間」とはみなさない許可行政庁もあります。
今回、第2種電気工事士の資格を持っているとのことですが、電気工事士には、第1種電気工事士と第2種電気工事士があり、第1種電気工事士の場合、資格を持っているだけで(実務経験なく)営業所技術者の要件を満たします(ちなみに建設業法による1級・2級電気工事施工管理技士の資格を持っている方も同様です)。
しかし、第2種電気工事士の場合、
①資格を取得して(免許交付後)から3年以上の電気工事の実務経験が必要とされます。
②その3年以上の実務経験は、電気工事業の登録をしている会社や個人事業主のもとでの実務経験となります。つまり「電気工事業登録」をしていない会社等で、いくら働いても電気工事の実務経験にはなりません。
③(東京都の場合)3年以上の実務経験期間中の常勤性を「健康保険被保険者証の資格取得年月日」や「厚生年金被保険者記録照会回答票」「健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書」「住民税特別徴収通知書(特別徴収義務者用)」もしくは「確定申告書」等で証明できることが必要になります。
以上のように第2種電気工事士の資格で建設業許可を考える場合、条件が出てきます。
建設業の許可通知書を失くしてしまった場合、再発行してもらえますか?
再発行できません。
許可通知書は、許可の申請に対する許可処分の通知であり、再発行できません。代表者や商号に変更があっても、許可通知書はあらためて発行しません。許可があることの証明がほしい場合や、変更を反映した文書が必要な場合には、許可証明書(1通400円)を請求する必要があります。
絶対になくさないよう保管してください。
建設業の書類は何年間保存しないといけないでしょうか?
建設業法では決まりはありません。
領収書に関しては、法人だと原則7年間、個人事業主の場合、原則青色申告だと7年間、白色申告だと5年間保管する必要があります。(白色申告の場合でも、消費税の課税事業者となっている個人事業主は、領収書を7年間保管しなければいけません。)
これから建設業許可取得を考えている業者の方は、専任技術者を実務経験で証明する場合1業種に付き10年分以上の工事請負契約書(ない場合、工事注文書と工事注文請書、または請求書と通帳の写し等)が必要となるので、10年分は保管しておくのが望ましいと思います。
また、すでに建設業許可業者も経審をやる会社は直近3年分の決算届や前回の経審申請書が必要になります。許可証と許可申請書の副本は10年分、決算届は直近5年分くらいは保管しておいたほうがいいです。
建設業許可の更新はいつまでにすればいいですか?
原則、許可期限日の約1か月前までに提出(申請)。
あくまで申請(書類の提出)が約1か月前までであって、書類の作成や収集にも時間がかかりますので、有効期限の切れる数か月前から行政書士を探しておくなり動き始めるようにしましょう。
元請けとなる大手建設会社は下請け建設会社の建設業許可期限を把握しているため、大手建設会社と取引をしている建設会社は注意です。許可期限が近づいてくると新しい許可証コピーの提出を求めてきます。その際にまだ更新取れていないとわかると大手建設会社からの信用が落ちてしまうこともあります。
千葉県では、有効期間満了の30 日前を過ぎた場合、理由を付記した始末書(任意様式)の添付が必要となります。さらに、有効期間が1 日でも過ぎてしまった場合は、更新の許可申請をすることはもうできません。あらためて新規で許可を申請することになります。新たに許可を取りなおすことになるため、許可番号も変わってしまいます。申請書類も増え、行政書士への報酬も増額し、行政への申請手数料も5万円から9万円に増額します。くれぐれも更新期限にはご注意ください!
業種追加で複数業種を申請する場合、手数料は業種ごとに計算するのですか?
業種の数ではなく、一般建設業・特定建設業の別によります。
手数料の金額は、業種の数ではなく、一般建設業・特定建設業の別で変わります。
全ての業種がどちらか一方なら5万円、一般と特定にまたがる場合は10万円といった計算になります。
他から営業所技術者を入れて追加の許可をしたいが社会保険に入れなくても大丈夫でしょうか?
社会保険の加入は建設業許可の要件のひとつでもあるため、認められません。抜け道や裏ワザはありません。
建設業許可の廃業届を出したら、いつの日付で廃業になるのですか?
廃業届(様式第22号の4)にある「廃業等の年月日」の欄の日付ではなく、廃業届が提出された後に行政庁が許可の取消し処分をした日(行政庁が届を受理した日)が廃業日になります。
許可後の質問
先日、弊社の求人募集で外国人からの応募がありました。
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」と聞いています。 その場合、現場作業者として雇用することは可能でしょうか?
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」と聞いています。
技術・人文知識・国際業務は専門性を持った資格で、現場作業(現業)は原則認められていません。 <外国人の方が、建設業で現場作業者(技能者)として働く場合> ・技能実習(2027年4月~育成就労に移行予定) ・特定技能 ・定住者(日系〇〇人)、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の身分系の在留資格 ・週の労働時間が28時間以内の家族滞在、留学生(資格外活動許可を取得している場合) などの在留資格が必要になります。 逆に、現場作業ではなく、施工管理(現場作業をしない技術者)、図面設計者などでの雇用でしたら専門性のある「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で雇用することができます。
現場作業に従事できる在留資格
| 時間制限なく就労できる資格 | 週28時間以内なら就労できる資格 | |
|---|---|---|
| ・技能実習(2027年4月~育成就労に移行予定) | ・家族滞在 (日本人、定住者、永住者以外の家族) | |
| ・特定技能1号、2号 | ・留学 | |
| 身分系の資格 | ||
会社(営業所)を移転する予定があるけど、建設業の手続きで何かやっておくことはありますか?
営業所の所在地に変更があった場合、変更後30日以内に変更届を提出が必要です。他にも会社名、資本金額、役員の新任・退任・改姓等の変更、代表者の交替などがあった場合には変更後30日以内の変更届が必要となります。
また建設業許可の要件でもある経営業務の管理責任者(常勤役員等)が取締役から退任する場合や、営業所(専任)技術者の退職・転勤等による変更がある場合は、変更後2週間以内に変更届の届け出が必要になります。届け出に期限があるため、変更前にご連絡ください。
将来的なことを考えて、会社にもう1人役員(取締役)を入れることにしました。(現状、許可要件の経営業務の管理責任者でも営業所技術者になるわけでもありませんが)建設業の方で何か手続きは必要ですか?
すでに建設業許可を持っている会社さんが、役員(取締役・代表取締役)を新任・交代・退任する場合、常勤・非常勤にかかわらず変更後30日以内に変更届を提出が必要です。監査役の場合は不要です。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お問い合わせ・ご相談は、お電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。まずはお気軽にご連絡ください。
| 営業時間 | 10:00~21:00 |
|---|
| 定休日 | 日曜・祝日 |
|---|